東京・豊洲にある「チームラボプラネッツTOKYO DMM」。
来場者が裸足になり、膝下まで水に浸かりながら作品と一体となる「水に入るミュージアム」は世界中から注目を集めています。
その一方で、「水は汚くないの?」「深くないの?」などと疑問に感じる人も少なくありません。
そこで今回は、チームラボの水は汚いのか、深さや回避方法について紹介していきたいと思います。
今回まとめた内容はこちら
- チームラボ豊洲の水は汚いのかについて
- チームラボ豊洲の水の深さについて
- チームラボ豊洲の水の回避方法について
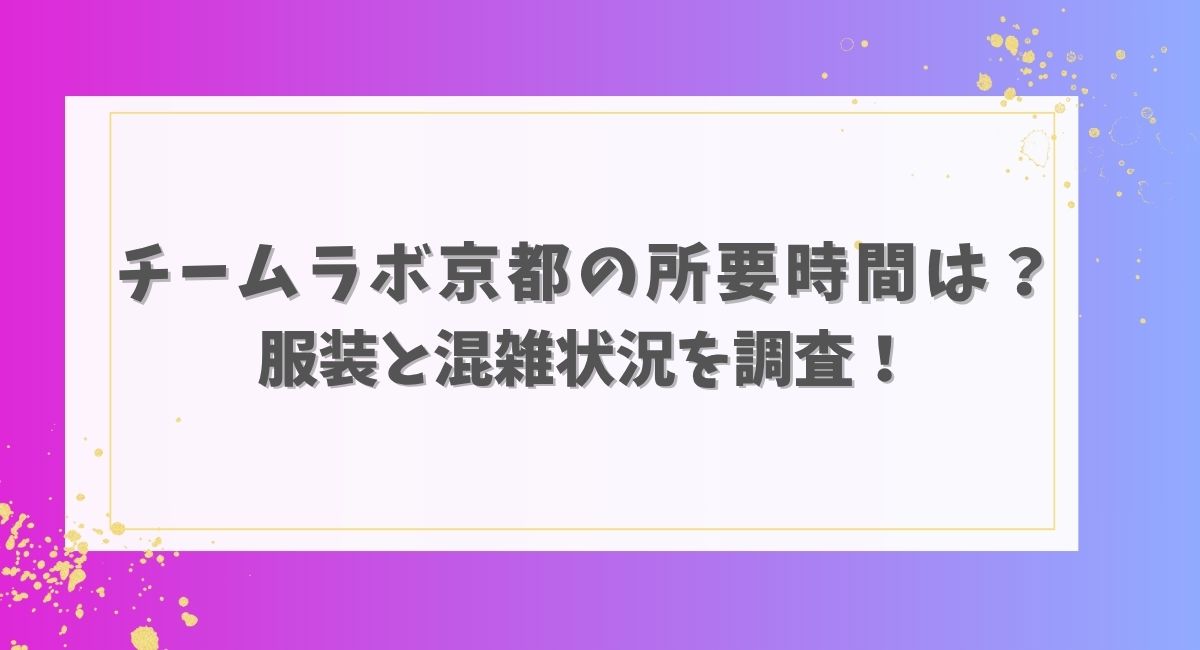
チームラボ豊洲の水は汚い?
チームラボ豊洲の水は汚いのかについて紹介していきます。
チームラボ豊洲の水を使用した作品「水に入るミュージアム」は、
しっかりと衛生管理がされています。
水は常に循環されており、塩素濃度も定期的に管理されています。
そんなチームラボ豊洲で管理されている項目は次のとおりです。
| 管理項目 | 管理している内容 |
|---|---|
| 水質の管理 | 濾過器で水を循環させ濁りを除去 |
| 水温の管理 | 体温に近い36℃前後に設定 冬でも冷たく感じないように調整 |
| 塩素の管理 | 約1時間ごとに塩素濃度を測定 基準値を維持 |
| 清掃の頻度 | 営業時間外に定期的な清掃を実施 |
| タオルの提供 | 鑑賞後には清潔なタオルを提供 |
それでも、不特定多数の人が裸足で入る作品のため、衛生面が気になる場合は
- ウェットティッシュ
- 小さめの足拭きタオル
を持参しておくと安心です。

作品を体験した後には、清潔なタオルが提供されるよ!
チームラボ豊洲の水の深さは?
チームラボ豊洲の水の深さについて紹介していきます。
水を使った展示作品が複数あるチームラボ豊洲。
水の深さは作品によって異なり、浅い場所もあれば膝下までしっかり水に浸かる場所もあります。
| エリア名 | 水の深さ |
|---|---|
| 坂の上にある光の滝 | 約10㎝ (足首程度) |
| 人と共に踊る鯉によって描かれる 水面のドローイング | 約30〜40㎝ (膝下〜膝丈) |
「坂の上に光る滝」は、緩やかな坂を流れ、歩き方によっては多少の水しぶきが上がることもあります。
一方、「人と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング」は、館内で最も水が深いエリアのため、
大人は膝下、子供は太ももあたりまで
浸かることがあります。
特に、子供と一緒に体験する際には足元に注意しましょう。
さらに、裸足での入場となる水のエリアでは、入り口で靴下を脱ぐ必要があるので、
- 脱ぎやすい靴
- タオル
- 替えの靴下
を持参しておくと、より安心して楽しめます。
チームラボ豊洲の水の回避方法は?
チームラボ豊洲の水の回避方法について紹介していきます。
水に濡れることが体験の一部となっているチームラボ豊洲の「水に入るニュージアム」。
そのため、基本的には水に触れる体験が中心ですが、どうしても水に入りたくない場合は、
近くにいるスタッフの方に声をかけて「水に入りたくない」
と、伝えてみましょう。
そうすると、迂回ルートを通って次の作品に進むことができます。
このルートはもともと車椅子の方のために設置されていますが、どうしても水に入りたくない方や赤ちゃん連れの方も利用可能です。
次に、濡れるのを最小限にする工夫や、濡れてしまった場合の対応方法についても見ていきましょう。
| 濡れるのを最小限にする工夫 | 内容 |
|---|---|
| 服装 | 濡れても良い服装 裾をまくれる服装がおすすめ スカートの場合は短めのものか着替えを用意しておくと安心 |
| 避けた方が良い服装 | スキニー タイツ ストッキング ロングスカート |
| 無料レンタル | ハーフパンツ(XS〜6L)とタオル 館内にて無料の貸し出しあり |
また、乳幼児や小さい子供が水の深いエリアに入る際には保護者の方が抱っこして鑑賞すると安心です。



自分に合ったスタイルで、思い切りチームラボ豊洲を楽しもう!
チームラボ京都についてはコチラの記事からご覧下さい。
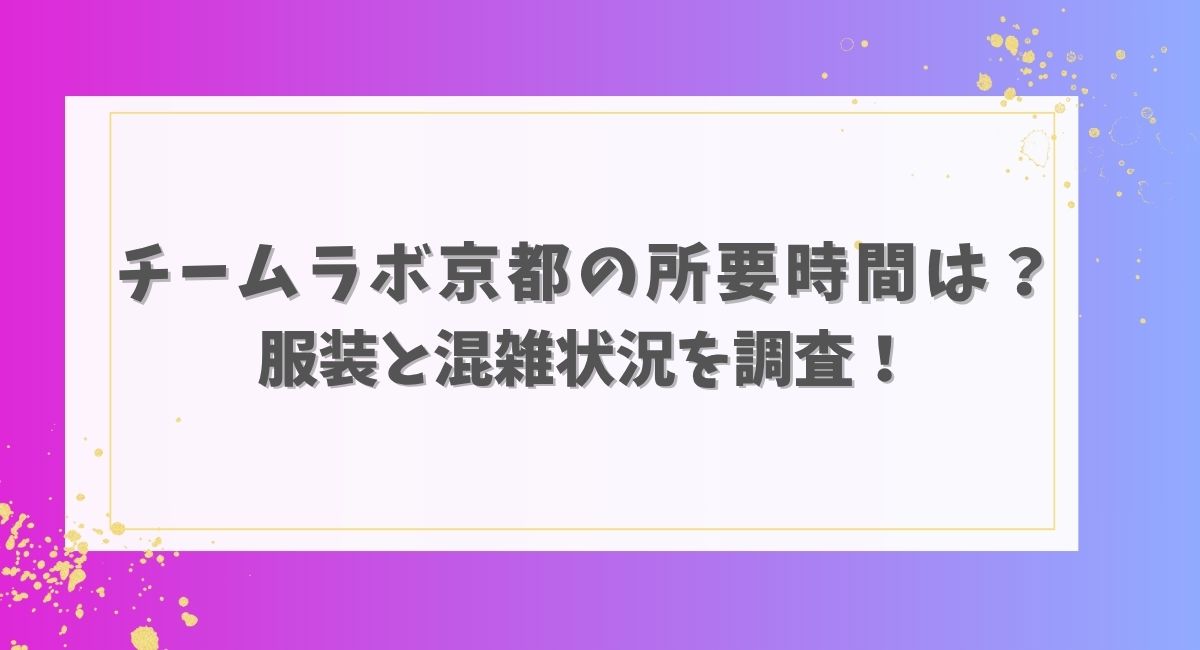
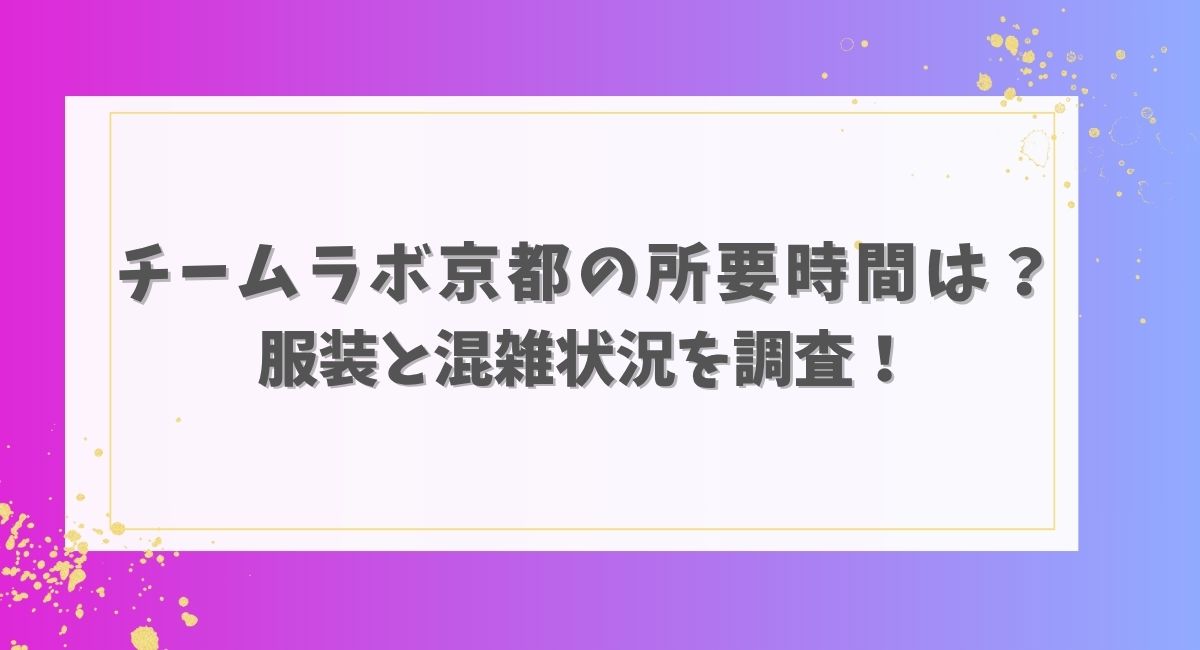
まとめ
今回は、チームラボ豊洲の水は汚いのか、深さや回避方法について紹介していきました。
日本各地にあるチームラボの施設の中でも、「水に入るミュージアム」は豊洲でしか味わえない作品です。
チームラボの施設に初めて訪れる方はもちろん、子供連れの方もちょっとの準備で心置きなくアートに没入してみてはいかがでしょうか。
最後までご覧いただきありがとうございました。
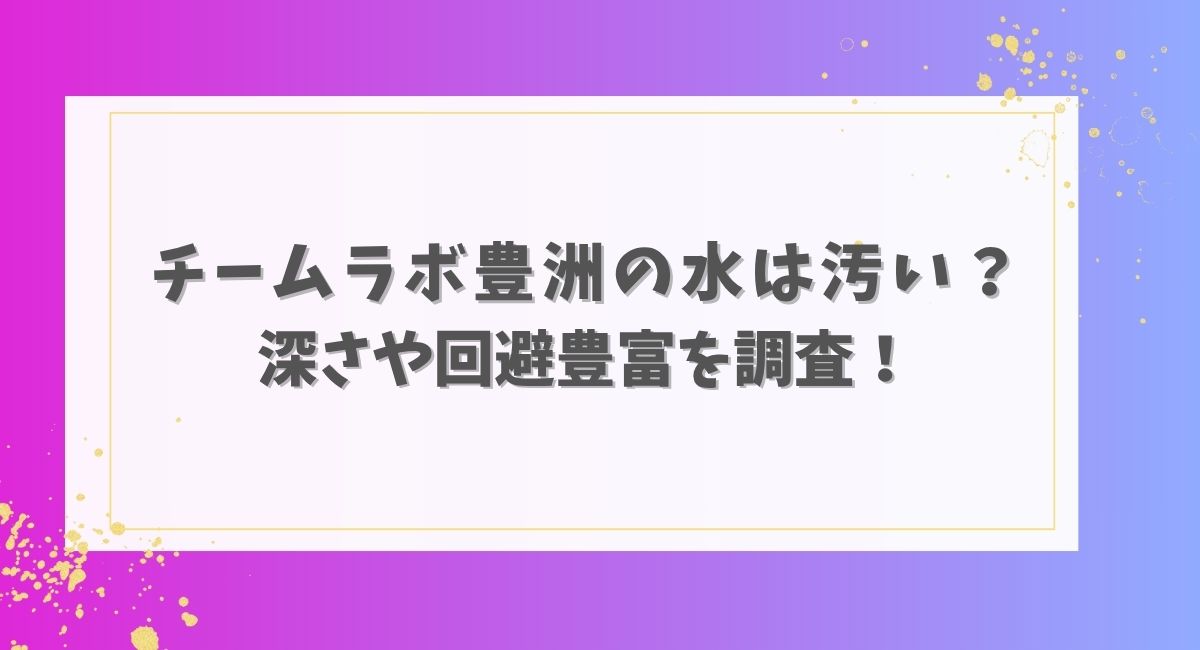
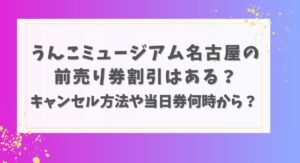
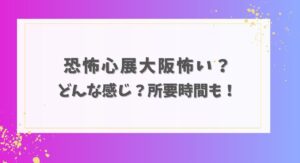
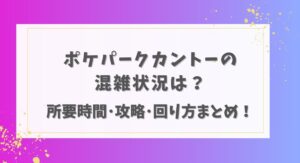

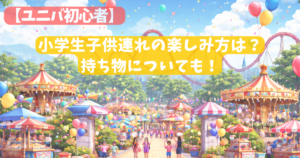
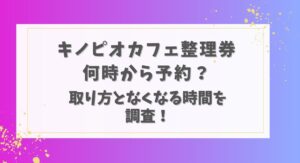
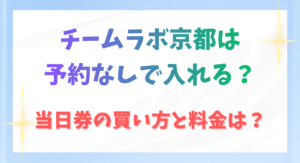
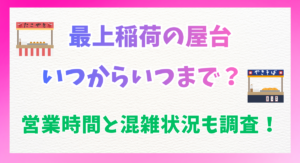
コメント